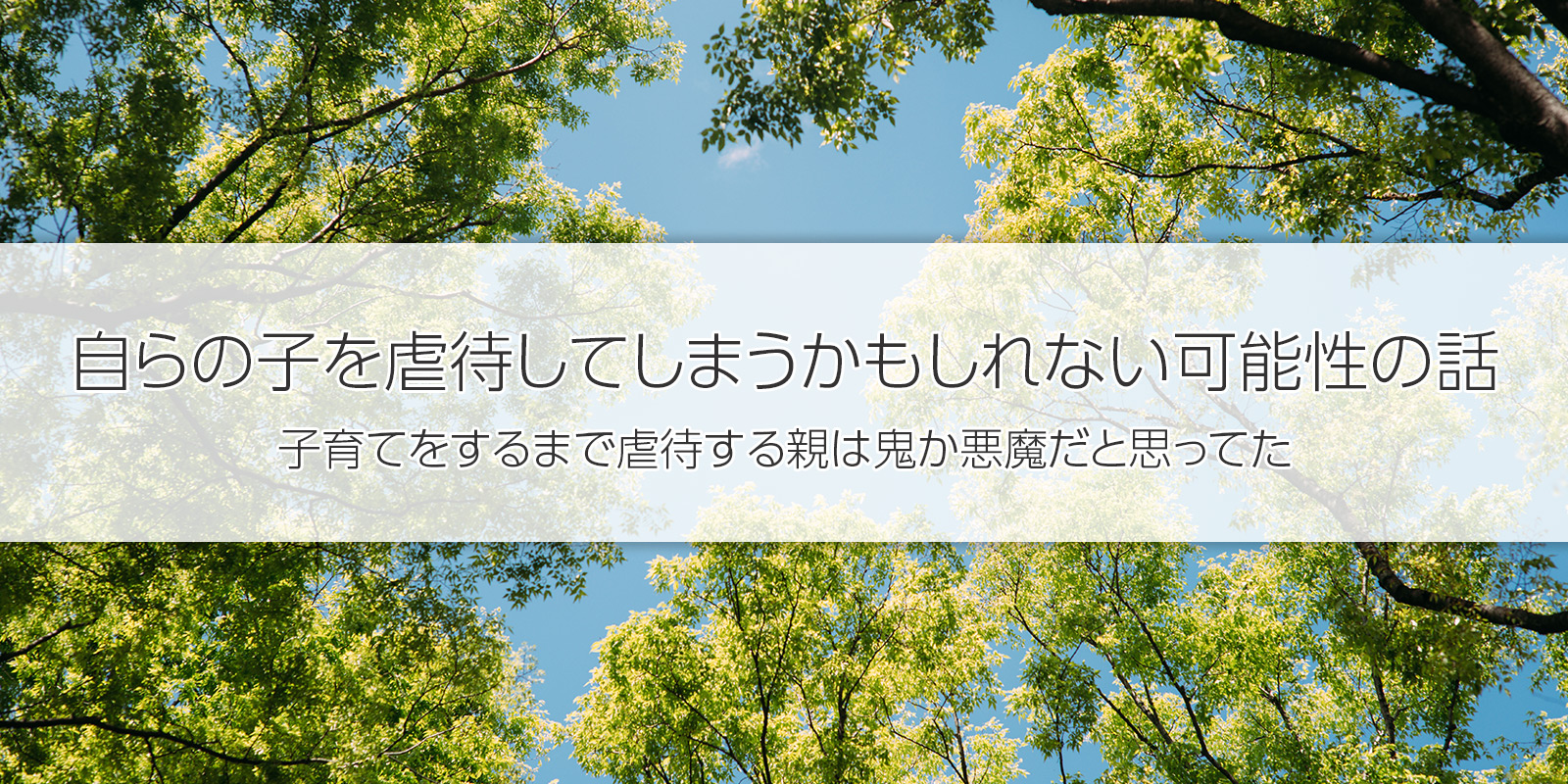痛ましい事件がおこり心がざわついたりします。
実は初報は見たくらいであまり詳しくは追っていません。精神的にその辺を追いすぎるとよくない予感がしているので。
なので、この記事自体は例の事件を直接話すものではないし、経緯もよく理解していないので、その辺の突込みがあってもスルーします。
我が子を虐待するという状況に陥る可能性に関して、そう低いものではない。
そう思う原因をまとめてみます。
自分が虐待する可能性に関して、前にツイートしたこともあります。
正直なところ虐待なんてすぐに手の届くところにいる。
圧倒的に弱者だし、周りに合わせるより自己の気持ちを優先する、子供という存在は、油断すると力(言葉も含)で支配し、コントロールしたくなりがち。
深く関わろうとすればするほど、突如湧き出る感情によって。
— 子育てとーさん (@kosodate10_3) 2018年5月25日
子育てに真剣に取り組むほど、昨今の家族の形態(核家族+ワンオペ)であると、虐待の危険性が高まります。
さらに、「子供は褒めて育てるもの」というはやりのスタイルだとさらにまずい。
ワンオペ問題
子供を育てるうえで、核家族というよりワンオペがまずい。
おそらくある程度、家事・育児をやってる男性だと2.3日のワンオペは余裕だと思うのです。
でも、それは2.3日だから。
終わりの見えるワンオペは、実はそこまでつらくないのです。
ワンオペ後どちらかというと達成感すら感じられる。
でも、終わりの見えないワンオペはまずい。
子供のペースやわがまま、いやいやに付き合わなくてはならない期間が、いつ終わるのかわからない状態で続く場合、不の感情を解消できず、積もり続けてしまう。
その行き場のなくなった感情は下手をすると、我が子に向かってしまうかもしれない。
されに、我が子に向かってしまったことによるショックはかなり大きいい。
生まれてからずっと、かわいいと思いながら献身的に育ててきたのならなおさら大きなショックとなってしまい、下手をするとネグレクトという別の虐待の可能性もでてきてしまう。
真面目に育てることの問題
最近の子育てのトレンドは「褒めて伸ばす育児」だと思います。
でも、これも結構むつかしい。
自分はそうは思っていても怒ってしまうことが多いし、機嫌の悪さを子供にぶつけてしまうこともあります。
とはいえ、フォローもしているし、親も人間だからそんなもんだよと学んでくれたらいいなと、子供に投げている部分もあります。
でも、真面目にほめて伸ばす系の育児をしてしまうと、怒りの感情が芽生えた際や、思わず手が出てしまったときに、自らの心を健全に保つのが難しくなるのではないでしょうか?
さらにワンオペとかだったり、パートナーがあまり子育ての話題を共有してくれなかったりしたら。
真面目であればあるほど負のループに入ったら抜け出せなくなりそうです。
子育てをするまで虐待する親は鬼か悪魔だと思ってた
結局何が言いたいのかといえば、虐待は誰にでも起こりえるかなり近くにあるものだということ。
自分が子育てをちゃんと取り組むまで、虐待なんてする親はなにか問題を抱えてたり、元々ひどい人間なんだろうと思ってました。
でも、今は全く違う。
幸せそうに子供を抱っこしながら歩く、そこの親子も。
子供の楽しい話題をツイートするお父さんも。
等しく虐待の可能性は存在していて、いつ間違いが起きても何ら不思議ではない。
それは、元々鬼畜な性質があるとかでなく、逆に真剣に子育てをしていたりする方が、よっぽど虐待に近い気がする。
真剣であればあるほど、追い込まれたときあぶない。
では、どうすればいいのか?
専門家でもないので、正しい解決法はわかりません。
でも、少なくとも子育ては一人で抱え込むべきではないと思います。
何かあったときに、別の目があれば思いとどまれるかもしれない。
Twitterで愚痴を吐き出すだけで、少しは心が軽くなるかもしれない。
リアルでもネットでも、一人で子供を育てているのではない。と思える状況にいることが少し虐待から自分を遠ざけてくれる気がする。
行政や法律が整備され、きちんと見守られる制度ができることは大切だけど、子供の成長は待ってくれない。
今できることをしながら、子供たちの将来や、自分の後輩たちの子育て環境が、よりやわらかで優しいものになっていくように、少しでも何かしていきたい。